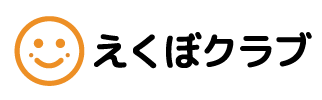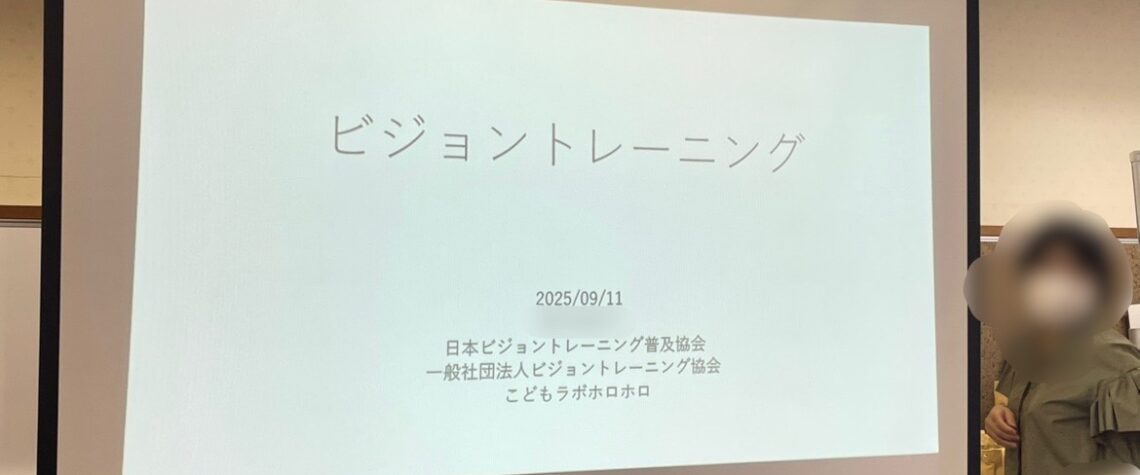2025年9月11日 学校部部会にて就学部、学校部、成人部の親御さんを対象に勉強会を開催しました。
講師は子育て中に大学でも学ばれ、臨床心理士の資格を取得し、現役で療育の仕事に携わりながら、保育部で親子でやるワーキングメモリを指導してくれている、えくぼクラブに所属しているお母さんです。
今回の勉強会では、ビジョン=発達に遅れがある子供たちの見る力がどのくらいあるのか?が大きなテーマでした。
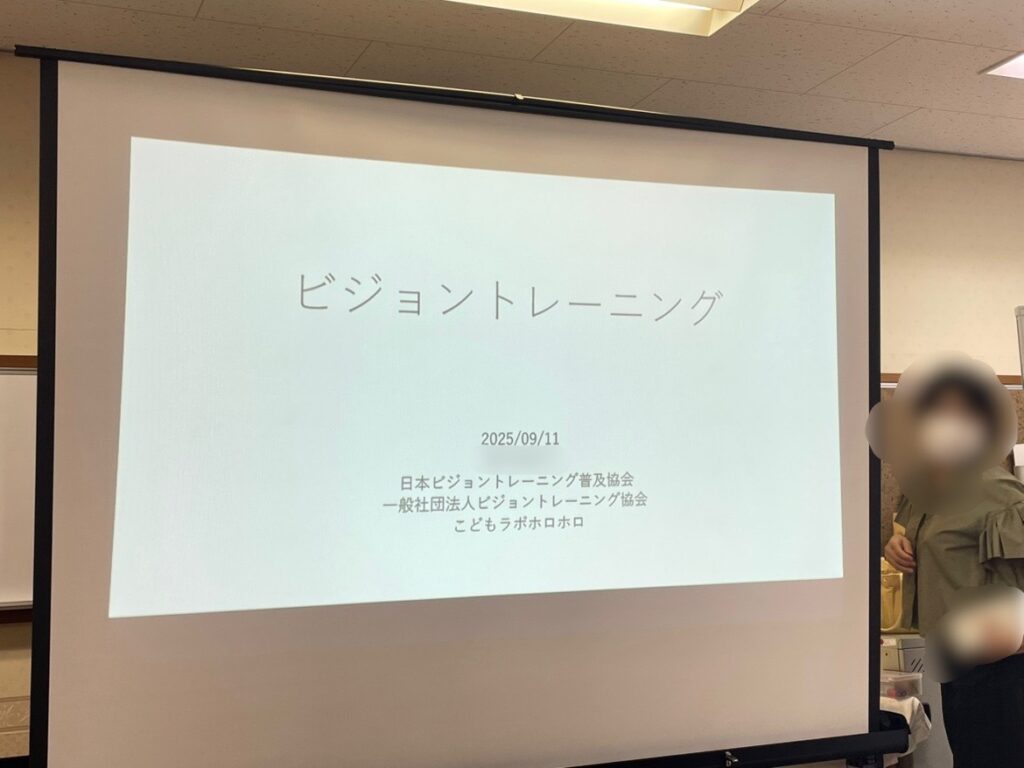
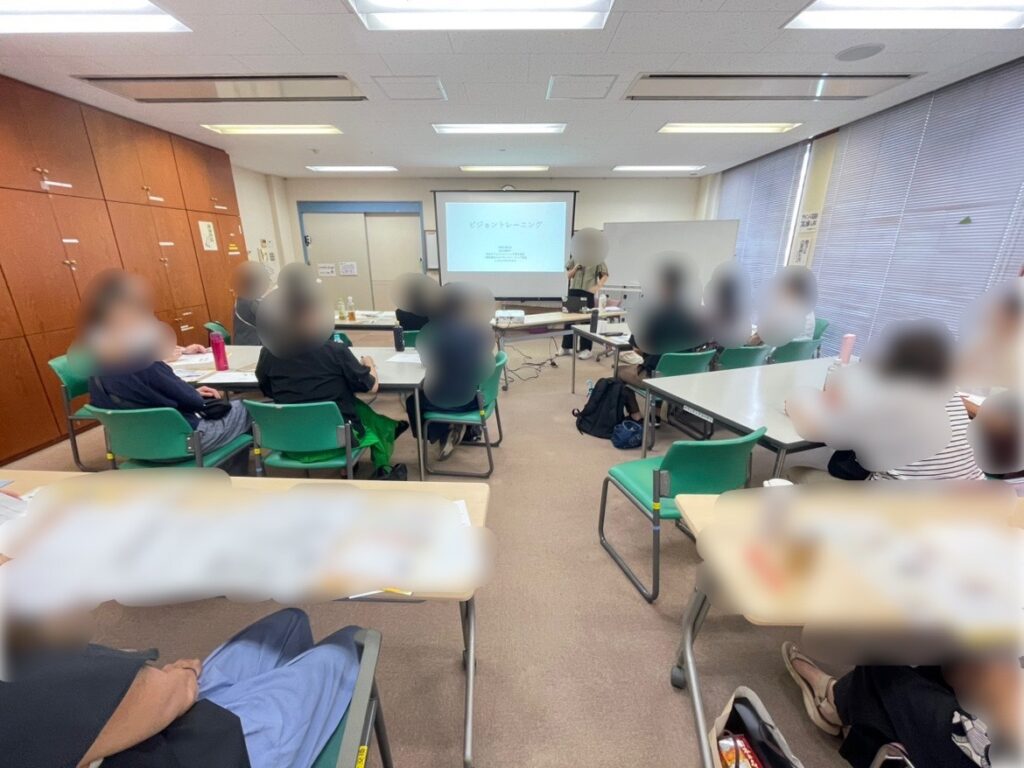
見る力とは。。。眼で見た情報を脳で認識し、脳や体がそれに反応(運動、体感、行動、表現、ことば)する力のこと。
私たちはついつい、なんでうちの子は言葉がでないのかな?なんで座っていられないのか?なんでボールがキャッチできないのかな?とても手が不器用だな。と体の反応(結果)ばかりに目が行きがちになります。
今回の勉強会では、実際に見えずらさを体感するためにトイレットペーパーの芯を使って視界を制限した状態で特定のマークを探してみたり、あえて指を使わず眼球の動きだけで移動する対象物を追ってみたり、うちの子はこのような感覚で普段の生活を送っているのかな?と想像できる内容でした。
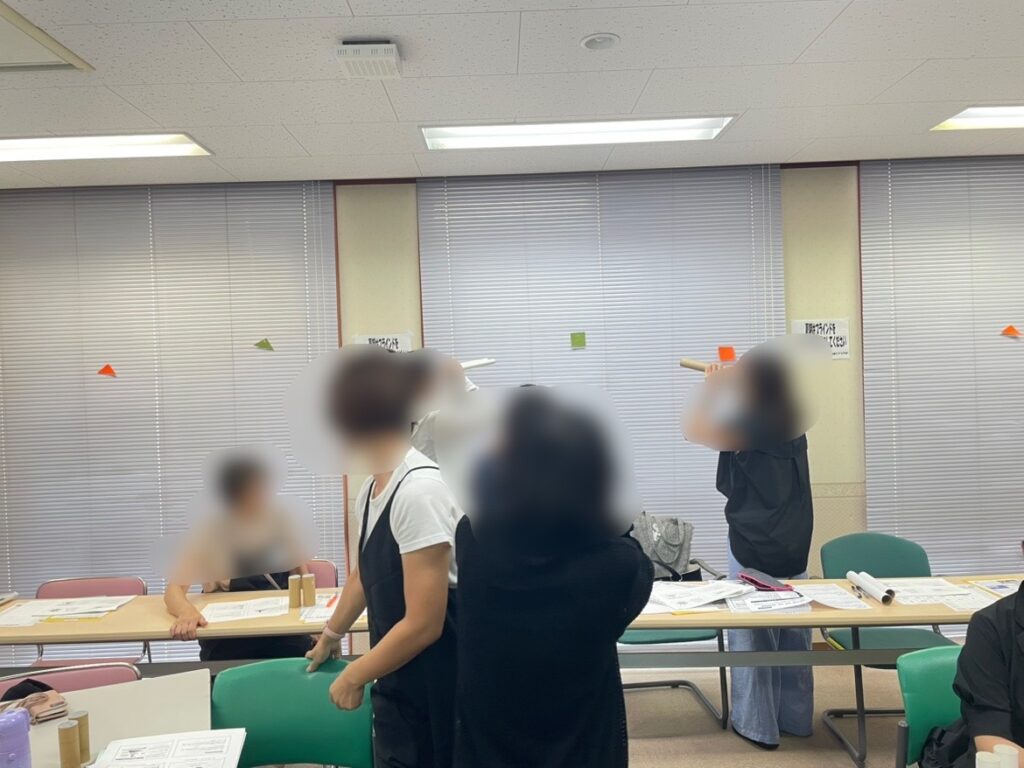
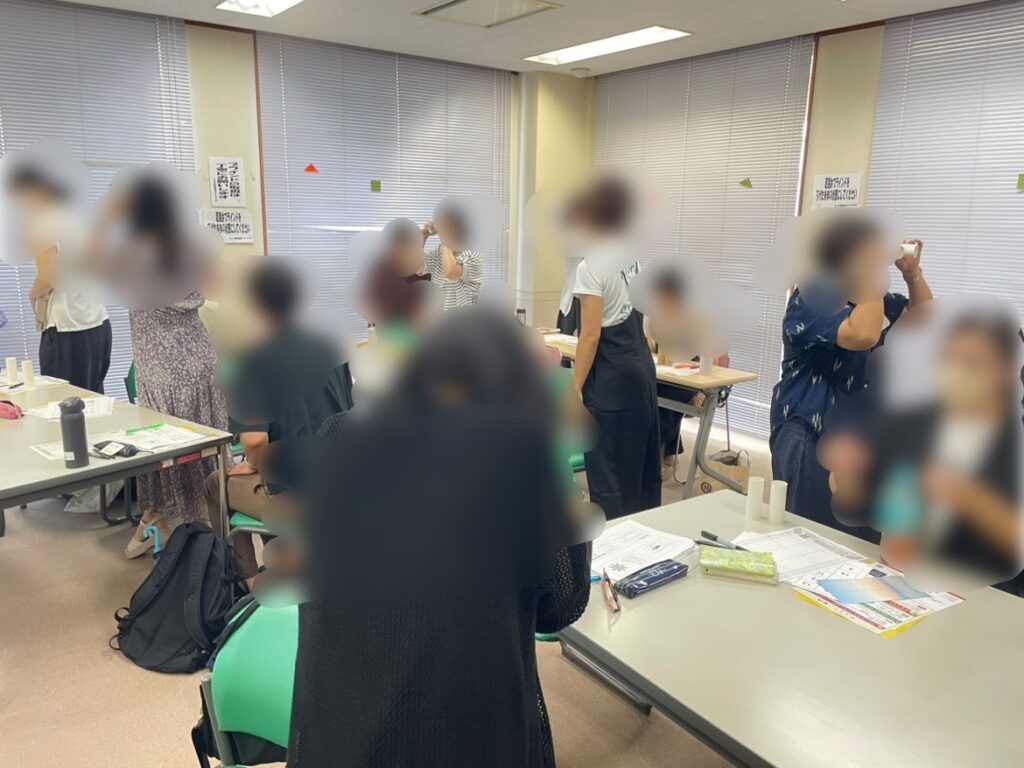
眼で見た物事をしっかり脳に伝達し、適切に情報処理をし、それに反応する力。(見る→認知する→行動する。)眼球運動は発達の順序からすると、①頭部から足②身体の中心から抹消③粗大運動から微細運動の一番最後の微細運動に属するそうです。①や②のしっかりとした発達の土台が出来上がっていない状態で③の微細運動(結果)ばかりを注意してしまうのは子供にとったらとてもストレスになりますよね。
講師の先生の「発達段階の忘れ物はないですか?」の言葉が心に響きました。
普段の生活の中で楽しみながら子供と一緒に体を使って遊ぶ、感覚を養っていくことがいかに重要か、改めて考えさせられる勉強会でした。
===10月に保育部の活動でビジョントレーニングを実施しました!その様子はコチラ⇩===